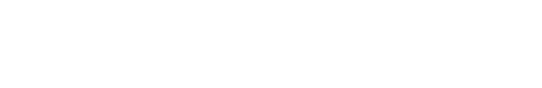- 【遺伝学から見た食卓革命】 第1回 江戸時代の遺伝学
- 【遺伝学から見た食卓革命】 第2回 ゲノム情報の光と影
- 【遺伝学から見た食卓革命】 第3回 すごい「トウモロコシ」の作り方
- 【遺伝学から見た食卓革命】 第4回 食卓に並ぶ農作物のクローン技術
【遺伝学から見た食卓革命】 第5回 農作物の自殖と他殖
2015/08/21 10:00
↑カバー画像を押すと動画が再生できます。
はじめに
これまで4回のコラムを通じて、「江戸時代の遺伝学」、「ゲノム情報の光と影」、「すごい『トウモロコシ』の作り方」、「食卓に並ぶ農作物のクローン技術」について、農作物の遺伝や品種改良などを中心にお話してきました。
最終回となる今回は、植物における開花・受粉・受精を経た「生殖過程」の科学的基盤についてお話したいと思います。種子・果実が農作物として生産(子実生産)される際、受粉・受精がきちんと機能することで初めて子実形成が起きる、ということは簡単に第1回でも触れましたが、今回はさらに詳しくお話していきたいと思います。
なお、最初(画面上のタイトルカバー)の動画は、雌しべの先端・柱頭に花粉(金色の米粒のように見える)をのせた時、花粉がどのように変化するかについて、観察し、再生時間を縮めたものです。花粉は水を吸い上げ(吸水)、ふくらみ、この動画では少し見にくいですが、花粉管を発芽させることもあります。
自殖性、他殖性とは
花粉を雌しべの先端・柱頭に付着させることを「受粉」と言い、花粉の中の精細胞と卵細胞が融合することを「受精」と言います。
一般的に植物の花の中には、雄しべと雌しべが同居していますので、同じ花の中で受粉・受精が起きると思われている方が多いかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
被子植物は自分の花粉で受粉・受精することができる「自殖性植物」と、他人の花粉でしか受粉・受精が成立しない「他殖性植物」に分類されます(仕組みなどは後述)。
自殖性植物の代表はイネであり、他殖性植物の代表はキャベツ・ハクサイ・ダイコン等のアブラナ科植物でしょうか(図1)。もちろん、自殖性植物のイネであっても他品種の花粉が付着し受精することもありますし、他殖性植物のキャベツも花の季節の終盤である春の終わり頃には、自分の花粉で受精することがあります。
つまり、自殖性、他殖性という性質が、デジタルの1 vs. 0という世界ではなくて、その中間的な揺らぎの部分も存在するということを意味します。こうしたことは、小中学校理科では殆ど習わないため「植物は自分の花粉で受粉する」というイメージに繋がるのかもしれませんし、中学校理科(昔は高校生物でした)で習う「メンデルの遺伝の法則(第1回【豆知識】参照)」で用いられていた材料が自殖性植物の「エンドウ」であることも大きく影響しているのかもしれません。
メンデルの実験の中に、エンドウの両親世代(F0)を相互交配して雑種(F1)を作出し、これを「自家受粉」してF2を作出する、という下りがありますので。では、植物には何故このような2つの受粉様式があり、それぞれの受粉様式には、どの様な利点・欠点があるのでしょうか。

自殖性、他殖性における利点と欠点
まず、他殖性の利点は、集団の遺伝的多様性が確保されることです。植物は動物とは異なり、特定の場所で生長を始めたら、そこから移動することができません。つまり、大きく変動する周囲の環境に適応しながら生きる必要があります。そうした環境適応性を広く身につけるためには、植物がつける種子、つまり子孫が遺伝的多様性に富んでいることが重要です。
集団が遺伝的に均一だと、その植物に対する病害虫が発生した時や、極端な温度・湿度変化等があった時、適応できずに全滅する危険性があるからです。この遺伝的多様性を確保するためには、訪花昆虫を花色や蜜で呼びよせ、花粉を運んでもらう等の高いコストを負ってでも、異なる遺伝的背景の花粉(精細胞)と卵細胞で種子形成することが重要です。しかし、近くに同種の花がない場合は、種子(子孫)を残せない可能性がある、という欠点もあります。
それに対して、自殖性の利点は、低リスクで多くの子孫を残せることです。環境がそれほど変化しない場合には、無理に遺伝的多様性を高める必要はありません。そのため、自殖を行って遺伝的背景が同じ個体を増やす方が、その植物種の繁栄にとって有利になる場合があります。ただし、自殖により遺伝的背景が均一になるために、生育環境条件の変化で全滅等の欠点があります。
他殖促進:タマネギに見られる雌雄異熟
では、他殖性植物がどのように他殖を促進しているのか、その仕組みを説明していきましょう。先述の通り、多くの植物には、雄しべと雌しべが同居していますから、自家受粉の確率が高くなります。それを避けるため、植物はいくつかの仕組みを発達させてきました。その1つが「雌雄異熟」というシステムです。
これは開花した時、「雄しべと雌しべの成熟するタイミングをずらす」という仕組みです。雄しべが先に熟する「雄性先熟」とその逆の「雌性先熟」があります。雄性先熟の例としては、タマネギ・トウモロコシなどがあげられます。タマネギと言えば、ねぎ坊主といわれる小さな花の集合体を形成しますが、小さな花の開花時に、雄しべが先に成熟して花粉が放出されます。その時にはまだ、雌しべは成熟していないため自殖では、種子形成が起きず、他殖性が担保されるという仕掛けです(図2)。

他殖促進:菜の花に見られる自家不和合性
もう1つ、さらに洗練・進化した仕組みが「自家不和合性」だと言われています。これは、雄しべ、雌しべが機能・形態ともに正常であるにもかかわらず、自家受粉の時には受精に至らず、他家受粉の時に受精に至る現象です(図3)。簡単に言えば、雌しべが自分の花粉と他人の花粉を識別できて、他人の花粉だけで受精するという仕組みです(詳細な仕組みは【補足】参照;http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/news2/2015/08/12162414.php
)。
アブラナ科野菜のハクサイ・カブ・ダイコン、バラ科果樹のリンゴ・ナシ・サクランボ、ケシ科のヒナゲシ、ヒルガオ科のサツマイモ、タデ科のソバ、カタバミ科のスターフルーツなどがあげられ、被子植物の半数が自家不和合性形質を有しているといわれています。
子実形成をしないで収穫するハクサイ・カブ・ダイコン・ケシ・サツマイモなどは、生産物に対して自家不和合性の影響が出ることは直接ありませんが、その他のリンゴ・ナシ・サクランボ・ソバ・スターフルーツなどでは、他家受粉することが果実・種子形成の必要条件となります。
サクランボで言えば、「佐藤錦」を生産する際は、遺伝的な性質の異なる品種「ナポレオン」などの「受粉樹」を近くに植える必要があります。もし、自宅でこうした果樹を植えている時、1つの品種しか植えてないにもかかわらず結実するときには、近所に同種で異なる品種の樹木があり、その花粉がハチなどの訪花昆虫によって運ばれていると思って良いと思います。このような現象を庭先で見つけたとき、近所に異なる品種の樹がないか探してみてはいかがでしょうか。

おわりに
今回は、著者がこの領域の研究に携わっていることもあり、少し難しい内容になったかもしれませんが、いかがだったでしょうか。この1週間、「遺伝学から見た食卓革命」というテーマで、江戸時代の日本人の品種改良から最近の農作物の品種・繁殖の現状、また、農作物がどの様に品種改良され、食卓に並んでいるのか、こうした品種改良の背景である遺伝学・ゲノム・受粉・受精に関する科学等を簡単に紹介してきました。
これらのことからなるほどと思って頂き、また、少しだけかもしれないですが、毎日の食生活、野菜・果物・花を見る眼が違ってきたら幸いです。これで著者の記事は終わりとなりますが、著者の研究活動に関すること、大学の研究室での日々の生活、著者がライフワークとして行っている出前講義のことなどを、研究室のホームページ(http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/)から日々発信しております。あわせてご覧頂ければ幸いです。この1週間、本当にありがとうございました。また、読者の皆様とどこかでこうした機会があることを楽しみにしております。ありがとうございました。

最後と