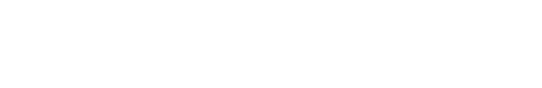「災害の神話学」第3回 天から火の雨が降ってくる
東北大学
2016/07/27 09:51
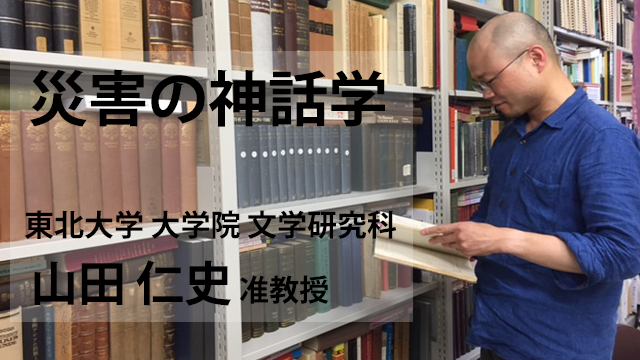
第3回 天から火の雨が降ってくる
おそろしい災害の神話——。ノアの洪水ではまだ足りないとでも言うかのように、『旧約聖書』には別の災厄も語られています。
〈ソドムの滅亡〉
ノアの子孫で、アブラハムの甥にあたるロトという男がやって来たのは、ソドムという風紀の乱れた町でした。神はこれに怒り、町を滅ぼすことに決めますが、ロトとその家族には「ふり向かずに逃げよ」と教えます。
日が昇ると、神は天からソドムの町に硫黄の火を降らせ、町と低地一帯を、そして全住民と大地の若草とを滅ぼしました。また、ロトの妻は後ろをふり向いてしまったので、塩の柱に変えられてしまった、と言います【図】。

デューラー「ソドムを逃れるロトと娘たち」
硫黄の火が天から降ってくる——火山の噴火のようなイメージでしょうか。なかなか想像しにくいのですが、同じような伝承は他の地域からも知られているのです。
〈インド・ムンダ族の火の雨神話〉
インドの中東部に暮らし、オーストロアジア語族に属する、ムンダ族・サンタル族の間には、火の雨が降ってきたという神話が多く伝わっています。
それによると、神は人類を地の塵から造った。しかしすぐに人類は邪悪になった。体を洗いもせず、働きもせず、いつも歌ったり踊ったりばかりしていた。
それでシング・ボンガ神は彼らを造ったことを後悔し、滅ぼすことに決めた。その目的のため、神は火の雨を天から下し、すべての人が死んだ。ただ兄妹二人だけが、木陰にかくれて助かった。こんな話です。
火の雨や大火災によって人間が死に絶えた、という話は他にもアメリカ大陸や東アジアにも伝わります。何とも、ものすごい想像力と思わずにいられません。
〈天が落ちてくる?〉
天から火の雨、というのではなく、もっと直接的に、天そのものが落ちてくるのでは、という恐怖もしばしば語られます。
有名なのは、『列子』天瑞にみえる杞憂(きゆう)の話ですね。中国古代、杞の国の人が、天が崩れ落ちてくるのではと心配したというもの。取り越し苦労をやや嘲笑する言葉でもあります。
しかし、同様の恐怖をいだいてきた民族は実は多く、東南アジアのマレー半島、ボルネオ島、南米ブラジルのトゥピ=グアラニーといった人々から知られる他、古代ケルトにもそうした観念がありました。
つまりギリシャのストラボンが著した『地理書』によれば、ケルト人は「あなたたちに恐ろしいものはいったい何か」と問われて、「天が頭上に落ちかかってでもこない限り、何も恐ろしいものはない」と答えたとされています。
ひるがえって21世紀の現代日本。ドローンがいつ落ちてこないとも限りません。「杞憂」と笑ってばかりもいられないようです。
次回は「第4回 雪と氷におおわれた世界」です。
次配信日程:7月28日(木) 予定
【プロフィール】
山田 仁史
東北大学大学院文学研究科准教授
宗教民族学の立場から、人類のさまざまな神話や世界観を研究中。
著書に『首狩の宗教民族学』(筑摩書房、2015年)がある。
ブログ「buoneverita」
http://buoneverita.blog89.fc2.com/
おそろしい災害の神話——。ノアの洪水ではまだ足りないとでも言うかのように、『旧約聖書』には別の災厄も語られています。
〈ソドムの滅亡〉
ノアの子孫で、アブラハムの甥にあたるロトという男がやって来たのは、ソドムという風紀の乱れた町でした。神はこれに怒り、町を滅ぼすことに決めますが、ロトとその家族には「ふり向かずに逃げよ」と教えます。
日が昇ると、神は天からソドムの町に硫黄の火を降らせ、町と低地一帯を、そして全住民と大地の若草とを滅ぼしました。また、ロトの妻は後ろをふり向いてしまったので、塩の柱に変えられてしまった、と言います【図】。

デューラー「ソドムを逃れるロトと娘たち」
硫黄の火が天から降ってくる——火山の噴火のようなイメージでしょうか。なかなか想像しにくいのですが、同じような伝承は他の地域からも知られているのです。
〈インド・ムンダ族の火の雨神話〉
インドの中東部に暮らし、オーストロアジア語族に属する、ムンダ族・サンタル族の間には、火の雨が降ってきたという神話が多く伝わっています。
それによると、神は人類を地の塵から造った。しかしすぐに人類は邪悪になった。体を洗いもせず、働きもせず、いつも歌ったり踊ったりばかりしていた。
それでシング・ボンガ神は彼らを造ったことを後悔し、滅ぼすことに決めた。その目的のため、神は火の雨を天から下し、すべての人が死んだ。ただ兄妹二人だけが、木陰にかくれて助かった。こんな話です。
火の雨や大火災によって人間が死に絶えた、という話は他にもアメリカ大陸や東アジアにも伝わります。何とも、ものすごい想像力と思わずにいられません。
〈天が落ちてくる?〉
天から火の雨、というのではなく、もっと直接的に、天そのものが落ちてくるのでは、という恐怖もしばしば語られます。
有名なのは、『列子』天瑞にみえる杞憂(きゆう)の話ですね。中国古代、杞の国の人が、天が崩れ落ちてくるのではと心配したというもの。取り越し苦労をやや嘲笑する言葉でもあります。
しかし、同様の恐怖をいだいてきた民族は実は多く、東南アジアのマレー半島、ボルネオ島、南米ブラジルのトゥピ=グアラニーといった人々から知られる他、古代ケルトにもそうした観念がありました。
つまりギリシャのストラボンが著した『地理書』によれば、ケルト人は「あなたたちに恐ろしいものはいったい何か」と問われて、「天が頭上に落ちかかってでもこない限り、何も恐ろしいものはない」と答えたとされています。
ひるがえって21世紀の現代日本。ドローンがいつ落ちてこないとも限りません。「杞憂」と笑ってばかりもいられないようです。
次回は「第4回 雪と氷におおわれた世界」です。
次配信日程:7月28日(木) 予定
【プロフィール】
山田 仁史
東北大学大学院文学研究科准教授
宗教民族学の立場から、人類のさまざまな神話や世界観を研究中。
著書に『首狩の宗教民族学』(筑摩書房、2015年)がある。
ブログ「buoneverita」
http://buoneverita.blog89.fc2.com/