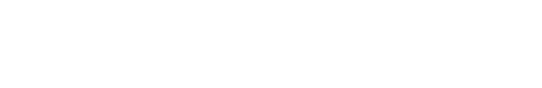「災害の神話学」第5回(最終回) 酷暑はヒトを滅ぼすか
東北大学
2016/07/29 10:00
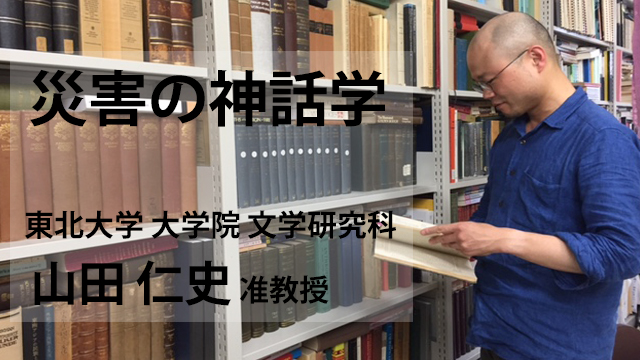
第5回(最終回) 酷暑はヒトを滅ぼすか
極寒の反対に、酷暑が人間社会をおそう神話もあります。
〈太陽を射たモグラ〉
日本では九州から中国地方を中心に、「太陽を射たモグラ」の昔話が分布します。これは災害というほどではないのですが、一例を挙げましょう。
昔ある所に、一匹のモグラがいたが、土の上に出ると天道様に照らされて、背中が熱くて困る。そこで、萩の木の枝を切って弓矢をこしらえ、天道様を射た。すると天道様に穴があいて暗くなった。それ以来、日蝕というものができたという。ところが、やがてその穴が治るとモグラは罰を受けて死んでしまった。それで今でもモグラは地上に出ると死んでしまうという(岡山県)。
つまり、モグラが地下棲みの動物なのは、かつて太陽を射た罰だというわけです。面白いことに、とてもよく似た話がモンゴルからも知られています。
〈たくさんの太陽〉
つまりモンゴルには、かつて複数(3個、4個、または12個)の太陽があった。それで地上は非常に熱かった。ある名猟師がそれらを射たが、その罰として彼はマーモットに変身させられた。こんな神話があるのです。
マーモットというのは、モンゴル語でタルバガンと呼ばれ、リス科で地下に棲む動物です。モンゴルでは夏場の食料ともなっています。いずれにせよ、ここでも太陽を射た人が、地下に棲む動物になってしまったわけです。
こうした複数の太陽という伝承は、古くは中国・前漢の『淮南子(えなんじ)』に、次のように出ています。
堯(ぎょう)という皇帝の時代、十個の太陽が一緒に出た。そのため穀物が焼けこげ、草木も枯れてしまい、民衆には食べ物がなくなった。そのうえ怪物たちが暴れ回った。そこで堯は弓の名手である羿(げい)に命じてこれらを退治させた。羿はさらに九個の太陽を射落とした。
おそらく、古代中国に知られていたこの伝説が、周囲に伝播したのでしょう。日本やモンゴルの他、中国や東南アジア・南アジア・東北アジアの少数民族のもとに、類似した伝承が数多く伝えられていることから、そう推測できます。ところが、類話の分布は太平洋を越えて、北アメリカまで及んでいるのです【図】。

世界における「太陽を射る話」の分布
そして北米の大盆地地域に知られる話では、太陽を射た者がコットンテイル(綿尾兎)という、地下棲みの動物に変身させられています。これは、日本やモンゴルとの共通点として、注目されます。
〈災害の神話は警告する?〉
災害の神話は何を語っているのでしょうか。酷暑の神話に限ってみても、これは他人事ではなくなってきています。毎年、夏になると熱中症で死者が出て、海水温度も上昇中です。ひょっとすると、人間もまた大自然の一部であり、自然に対する畏敬の念を忘れてはならない、というメッセージを、こうした神話から受けとるべきなのかもしれません。
【プロフィール】
山田 仁史
東北大学大学院文学研究科准教授
宗教民族学の立場から、人類のさまざまな神話や世界観を研究中。
著書に『首狩の宗教民族学』(筑摩書房、2015年)がある。
ブログ「buoneverita」
http://buoneverita.blog89.fc2.com/
極寒の反対に、酷暑が人間社会をおそう神話もあります。
〈太陽を射たモグラ〉
日本では九州から中国地方を中心に、「太陽を射たモグラ」の昔話が分布します。これは災害というほどではないのですが、一例を挙げましょう。
昔ある所に、一匹のモグラがいたが、土の上に出ると天道様に照らされて、背中が熱くて困る。そこで、萩の木の枝を切って弓矢をこしらえ、天道様を射た。すると天道様に穴があいて暗くなった。それ以来、日蝕というものができたという。ところが、やがてその穴が治るとモグラは罰を受けて死んでしまった。それで今でもモグラは地上に出ると死んでしまうという(岡山県)。
つまり、モグラが地下棲みの動物なのは、かつて太陽を射た罰だというわけです。面白いことに、とてもよく似た話がモンゴルからも知られています。
〈たくさんの太陽〉
つまりモンゴルには、かつて複数(3個、4個、または12個)の太陽があった。それで地上は非常に熱かった。ある名猟師がそれらを射たが、その罰として彼はマーモットに変身させられた。こんな神話があるのです。
マーモットというのは、モンゴル語でタルバガンと呼ばれ、リス科で地下に棲む動物です。モンゴルでは夏場の食料ともなっています。いずれにせよ、ここでも太陽を射た人が、地下に棲む動物になってしまったわけです。
こうした複数の太陽という伝承は、古くは中国・前漢の『淮南子(えなんじ)』に、次のように出ています。
堯(ぎょう)という皇帝の時代、十個の太陽が一緒に出た。そのため穀物が焼けこげ、草木も枯れてしまい、民衆には食べ物がなくなった。そのうえ怪物たちが暴れ回った。そこで堯は弓の名手である羿(げい)に命じてこれらを退治させた。羿はさらに九個の太陽を射落とした。
おそらく、古代中国に知られていたこの伝説が、周囲に伝播したのでしょう。日本やモンゴルの他、中国や東南アジア・南アジア・東北アジアの少数民族のもとに、類似した伝承が数多く伝えられていることから、そう推測できます。ところが、類話の分布は太平洋を越えて、北アメリカまで及んでいるのです【図】。

世界における「太陽を射る話」の分布
そして北米の大盆地地域に知られる話では、太陽を射た者がコットンテイル(綿尾兎)という、地下棲みの動物に変身させられています。これは、日本やモンゴルとの共通点として、注目されます。
〈災害の神話は警告する?〉
災害の神話は何を語っているのでしょうか。酷暑の神話に限ってみても、これは他人事ではなくなってきています。毎年、夏になると熱中症で死者が出て、海水温度も上昇中です。ひょっとすると、人間もまた大自然の一部であり、自然に対する畏敬の念を忘れてはならない、というメッセージを、こうした神話から受けとるべきなのかもしれません。
【プロフィール】
山田 仁史
東北大学大学院文学研究科准教授
宗教民族学の立場から、人類のさまざまな神話や世界観を研究中。
著書に『首狩の宗教民族学』(筑摩書房、2015年)がある。
ブログ「buoneverita」
http://buoneverita.blog89.fc2.com/